書くことは考えること、今回はライティングスキルについて考えます。
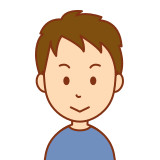
この文章はこんな人に向けて書いています。
・文章をうまく書けないと悩んでいる人
・ライティングのコツを学びたい人
「話すこと」と「書くこと」はまったく別の行為!
今回はライティングのバイブルともいえる名著、「20歳の自分に受けさせたい文章講義」について学んでいきます。
文章を書くときは、喜怒哀楽を表情で伝えることもできないし、声の調子などの使い慣れた武器も使えません。ただ言葉一本で表現することを迫られます。
それでは、どうやって自分の気持ちを文章で伝えることができるのか。
もし、話し言葉から書き言葉へ変換するノウハウが分かれば、書くという行為のなかには、論理性の確立や思考の整理など、さまざま要素が潜んでいるます。書くというアウトプットの作業は、思考のメソッドでもあるのです。
ガイダンス
【問題点 書こうとするから書けない】
われわれが文章を書く上でぶつかる問題は、次の2点に集約されます。
①文章を書こうとすると、固まってしまう・・・スタート段階でぶつかる壁
②自分の気持ちをうまく文章にすることができない。・・・書き始めた後にぶつかる壁
頭の中にはたくさんの思いが駆けめぐっている⇒頭の中をぐるぐると駆けめぐっているのは言葉ではない言葉以前の、茫漠たる、感じである。分からないことがあったら、自分の言葉に翻訳しましょう。
頭の中のぐるぐるを、伝わる言葉に翻訳したものが文章です。
われわれは書くという作業によってアウトプットし、ようやく自分なりの解を得ています。
翻訳の基礎を身につけるための「3つの再」
①再構築‥自分の言葉で話すことで内容を再構築する。
②再発見‥自分の言葉に翻訳する過程で、語り手の真意を「こういうことだったのか!」と再発見する。
③再認識‥自分がどこに反応し、なにを面白いと思ったのか再認識する。
思うままに書こうとせず、頭の中に漠然としているるぐるぐるを翻訳する、このことを頭に叩き込みます。
文章とは頭の中のぐるぐるから、伝わる言葉に、翻訳したもの。
そして、この講義を読み進めて行く際に、翻訳の意識を忘れずに!
文章は「リズム」で決まる

文体の2つの要素
①文章の語尾に注目し「です・ます調」と「だ・である調」を使い分けること
②「私」「僕」「俺」「筆者」といった主語を使い分けること
この2つの要素で決まるといわれてますが、それだけでは足りていません。
それでは何が足りていないのでしょうか?
結論「文体とはリズム」である。
リズムの悪い文章とは、端的に言えば「読みにくい文章」のことです。文と文とのつなげ方、展開の仕方がおかしいとき、その主張は支離滅裂になり、リズムよく読めなくなります。
文章のリズムは、「論理展開」によって決まります。
話す言葉をそのまま文字にしても、声や表情など伝えていた情報は必ず抜け落ちてしまいます。その抜け落ちた部分を捕捉しないと伝わる文章にはなりません。
話し言葉⇒書き言葉への翻訳が必要です
どうすれば支離滅裂な文章にならずにすむのでしょうか?
キーワードは接続詞にあります
「そこに接続詞が入るかどうかチェックする」
こうして論理破綻のキーワードである接続詞を意識するだけで、文章は論理破綻しにくくなります。
文章の視覚的リズム
リズムの悪い文章とは、端的に言えば「読みにくい文章」のことです。文章のリズムは、「論理展開」によって決まります。
こうして接続詞を意識するだけで、文章は論理破綻しにくくなります。
読者は文章を目で読んでいる。当然、書き手も視覚的なリズムを考えなければいけません。
視覚的リズム 3つによって生まれる
①句読点の打ち方・・・句読点は「1行にひとつ」。物理的なスペースが生まれ文章の切れ目を分かりやすくする。
②改行のタイミング・・・最大5行あたりをメドに改行する。改行には伝えたいメッセージを居徴する役目もある。
③漢字とひらがなのバランス・・・バランスを整えることで「字面そのものが持つ」圧迫感をなくす。
音読して聴覚的リズムをチェックする
音読は自分に客観性を持たせる助けとなる
音読する際のポイント2点
①読点「、」の位置を確認する・・・自分の意図する箇所に「継ぎ目」として読点が入っているか、音読でチェックする。
②言葉の重複を確認する
断定はハイリスク・ハイリターン
断定とは言い切ってしまうことです。断定の言葉は切れ味が鋭いので、断定の箇所の前後をしっかりとした論理で固める必要があります。
断定した箇所の前後2~3行には細心の注意を払います。
なぜなら、断定をすると条件反射として反発が出てきます。そして、論理の破綻した箇所から読み手は攻めてきます。
力強く断定すると、それだけで言葉に説得力が生まれます。言葉に説得力が出るとと、自信が湧いてきます。
読み手は説得力のある言葉を求めており、言葉の説得力は「断定というリスク」を取ることで得られます。
構成は眼で考える
文体の妙、文章の個性、あるいは文章の面白さ。これらを決めているのは、ひとえに構成であり、論理展開である。
文章の面白さは「構成」で決まる
文章を書く際に書きやすい3部構成「序論・本論・結論」
おすすめなのが映画などの映像表現を参考にするというもの
カメラワークを考える。
文章を書く人も、もっと文章におけるカメラ=眼の存在を意識するべきだと思います
①導入・・・客観のカメラ(遠景)⇒序論
②本編・・・主観のカメラ(近景)⇒本論
③結末・・・客観のカメラ(遠景)⇒結論
①の序論で語るのは、客観的な状況説明。カメラはずっと遠い地点から俯瞰で対象をとらえています。
続いて②の本論で語るのは、それに対する自分の意見であり、仮説です。カメラは対象にグッと近寄り、限りなく主観に近いポジションから対象を描いていきます。
そして、③の結論では、客観的な視点に立って論をまとめてい来ます。展開された自らの意見を風景の一部=動かしがたい事実として描きます。
文章全体にメリハリがついて、リズムもよくなります。
導入は映画の予告編のつもりで
読者はいつも「読まない」という最強のカードを手にして、文章と向かい合っています。いかにして読者の期待を煽り、本編まで読み進めてもらうか。
導入がつまらないと、読者は文章を読んでくれません。
【3つのパターンの導入例】
①インパクト優先型・・・導入のカメラの基本は遠景から。しかし、いきなりインパクトのある結論を持ってくる。
②寸止め型・・・もう少しで正体を突き止められるという寸前まで情報を開示。核心部分は見る人の想像させる。
③Q&A型・・・導入とは逆に早く見る人に情報を与え興味を持ってもらう。
【論理的な文章の3層構造】
論理的であるとは、すなわち「論が理にかなっている」ということ。
①主張・・・その文章を通じて訴えたい主張「論」
②理由・・・主張を訴える理由「理」
③事実・・・理由を補強する客観的事実
自分の主張が確かな理由によって裏打ちされたとき、その文章は「論理的」だといえる。
読者は文章を読むとき、「この人は何が言いたいんだ?」と考えて読んでいます。主張が明確になることで文章全体が読みやすくなります。
文章を書く理由は1つ、読者を動かすためだ。自分が有益だと思った情報を伝えることで、読者の心を動かし、行動まで変える。
文章を書くことは、他者を動かさんとする、力の行使なのです。
自分の文章のなかに、主張、理由、事実の3つがあるか、そしてその3つはしっかりと連動しているか、いつも意識するようにしましょう。
本当のリアリティは、日常の何気ないところに転がってるので、細かい部分まで描写することによって生まれれます。
構成は眼で考える
文章の構成を考えるとき、頭の中で素材うをこねくり回してもうまくまとまりません。頭の中のぐるぐるを図解・可視化して、流れとつながりを明確化することができます。
読者の「椅子」に座る
文章には必ずそれを読む読者がいます。必要なのは相手の立場に立つこと、さらに必要なのは、隣に立つことではなく、読者と同じ椅子に「座ること」である。
我々の椅子に座れる読者は2人
①10年前の自分 10年前の自分に語り掛けるように書きます。
10年前のあなたと同じ問題を抱え、同じ景色をを見て、同じようにもがき苦しんでいる人は必ずいます。
今、この瞬間にも日本のどこかに「10年前のあなた」がいるからです。
②特定のあの人 多くのライターや編集者が陥ってしまうのが「多数派の罠」です。
多数派向けに中途半端に八方美人である文章は読者の心には残りません。
椅子に座る「たったひとりの誰か」ではなく、自分でもなく、もう一人の読者を想定します。
好き嫌いをはっきりさせること
好き嫌いをはっきりさせることで、書き手としての自分が見えてきます。自分がどんな文章を書きたいと思っているのか、その傾向が明らかになるからです。自分の嫌いを深く掘り下げていくと、最終的に書き手としての自分はどうありたいのか、という潜在的な欲求が明らかになってきます。
人は「他人事」では動かない
基本的にわれわれは、他人事には興味がありません。
当事者の一人として、読者を議論のテーブルに着かせることです。文章の早い段階で独自の仮説を提示します。一般論とは相反するような仮説です。
そして、読者に「あなたはこの仮説をどう思うか?」と問いかけ、読者と一緒になって、その仮説が正しいかどうかの検証作業にあたるのです。
●読者を巻き込む「起”転″承結」
起承転結のトラブルメーカーである「転」は、ほんの少し配置転換してあげるだけで大きな効果を発揮します。
●冒頭に真逆の一般論をもってくる。
ポイントは転ではなく、起です。冒頭にどんな一般論もってくるか?こそが、最も大切なのです。文章の「起”転″承結」を成立させるためには、冒頭の「自らの主張と真逆の一般論」をもってくる必要があります。
あなたの主張を正確な形で知っているのはあなただけであり、すべての読者はそれを知らない素人なのです。
文中にツッコミが入り、そこに答えていくだけで読者の疑念は晴れていきます。
大きなウソは許されるが小さなウソは許されない
細部をどれだけ大事にできるかは、文章を書く上で最重要ポイントの一つと考えていいです。
文章には自分の頭でわかったこと以外は書いてはいけません。
【読者が求める3要素】
①目からウロコ・・・「おおっ!!」「ええーっ!!」
②背中を後押し・・・「そうそう」「よしよし」
③情報収集・・・「ふむふむ」「なるほど」
①目が覚めるような読書体験 自己変革の欲求、刺激が欲しい、感動したいという欲求
②自説を補強しようとする自己肯定の欲求 自分が間違っていないことを確認したい、迷っている自分の背中を押してほしい
③冷静で客観的な意見を求めようとする欲求 世間の平均的な意見を知りたい、専門家の客観的な知識を知りたい
目からウロコは3割、残り7割はすでに分かっていることでよいです。
原稿に「ハサミ」を入れる
右手にペンを、左手にハサミを
推敲とは自分の書いた文章を読み返し、練り直すことです。ハサミを使った編集こそが、推敲の基本です。
書き始める前の編集・・・問題は「なにを書くか?」ではなく「なにを書かないか?」です。「なにを書かないか?」を基準に考えると、文章の内容は全く違ったものになります。発想が引き算になるからです。
【書かないものを見極める方法、2つの編集方法】
書き始める前の編集作業
まずは頭の中のぐるぐるを紙に書きだします。頭の中を可視化するには、紙に書きだすのが一番だからです。
【手順】
①テーマについて関連するキーワードを10個書き出す
②キーワードに傾向が見えてくる。
③それ以外のことに限定して、もう10個のキーワードを書き出す。
こうして、ある傾向を持つキーワードとそれ以外のキーワードの両方を出し尽くしたとき、ようやく元ネタが揃ったことになります。
自分に何重にも疑いの網をかけていくことで、ようやく書くべきことが見えてきます。見えてなかったものが見えてきます。
文章を書き終えてからの編集作業
推敲とは過去の自分との対話です。推敲をするにあたって最大の禁句が「もったいない」です。
どれだけ自分の「もったいない」や「せっかく書いたのに」を振り払い、文章を削ることができるか。
●論理性をチェックする方法→この文章を図に描き起こすことはできるか?
●細部がどれだけ描写できているかをチェックする方法→この文章を読んで映像が思い浮かぶか?
長文を見つけたらさっさとハサミを入れて、短く切り分ける
【長文を短く切る3つの理由】
①冗長さを避けてリズムをよくする
②意味を通りやすくする
③読者の不安をやわらげる
文章を書きながら行き詰ってしまったとき
いったん書くのをやめて、文章を最初から読み返します。
①文章を別のワープロソフトにコピー&ペーストする
②文章のフォントを変更する
③縦書き・横書きを変更する
視覚的にまったく別の角度から眺められるようになり、自分の文章に対してかなり新鮮かつ客観的に向き合うことができるからです。
1回ではダメ、2回は読み返します。
書く自分、読み返す自分、もう一度読み返す自分、と3人の自分によって文章をチェックしていきます。
まとめ
人はなぜ文章を書くのか?改めて考えてみる良い機会となります。
なかなか思い通りに文章が書けない。文章を書くのが苦手。そんな人に大変参考になる本です。もっと早くこの本に出合えていたら、文章を書くことがもっともっと苦にならず、好きななっていたはずです。
いい文章とは読者の心を動かし、その行動までも動かすような文章のことである。
参考図書
20歳の自分に受けさせたい文章講義
その他 時間がある方におすすめ
沈黙のウェブライティング


